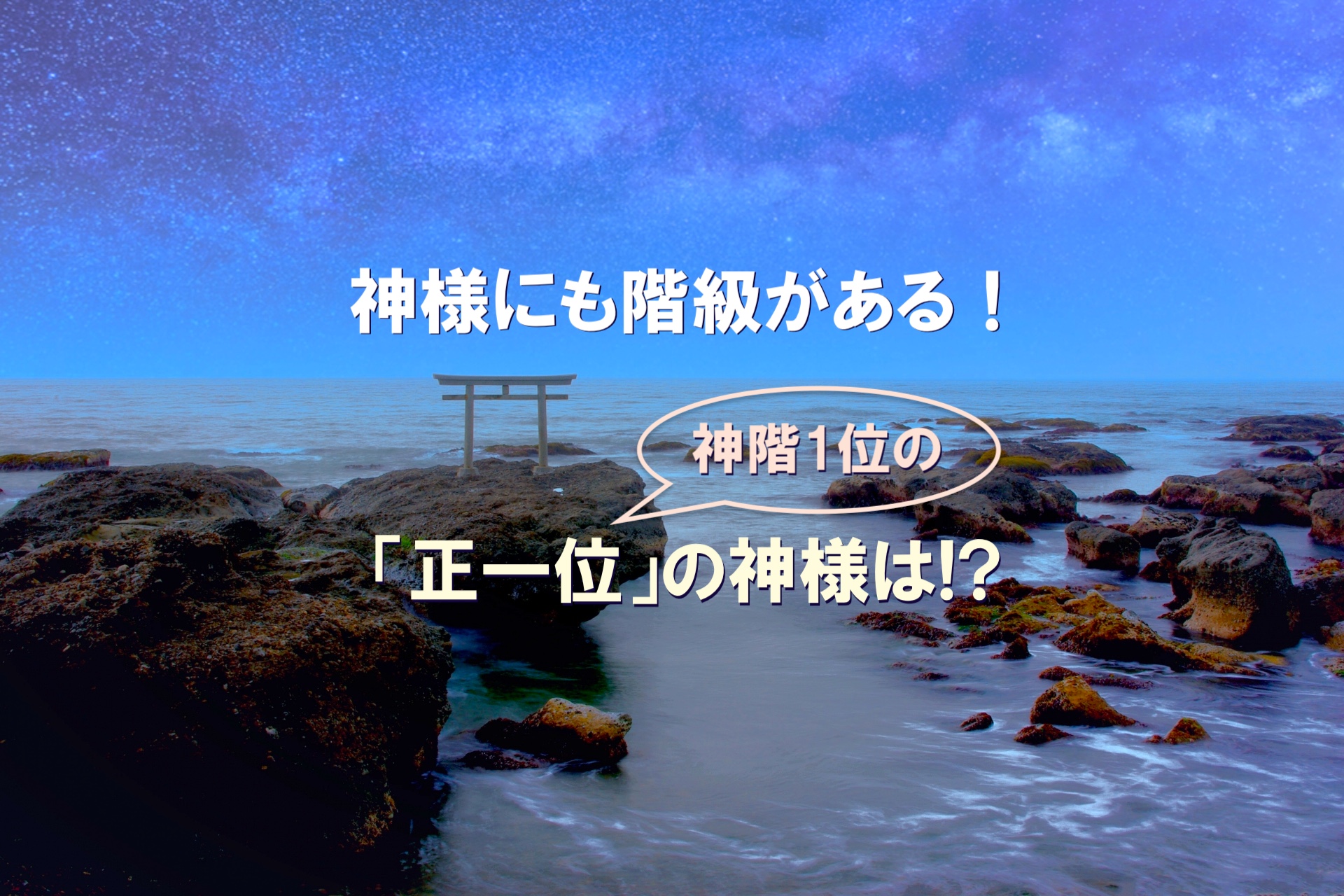実は神様にも位(くらい)、階級があることをご存知だろうか。「苦しい時の神頼み」という際にも、できれば、トップレベルの神様にすがりたいというのが人情です。平安時代に始まった神階は、現在では正六位(しょうろくい)から正一位まで15段階。神社に与えられたのが社格、神様に神階という構成ですが、時代によっても変遷しています。
稲荷神は従三位から正一位に特進

史書における神階の記載は、六国史(りっこくし=奈良・平安時代に編纂された『日本書紀』、『続日本紀』、『日本後紀』、『続日本後紀』、『日本文徳天皇実録』、『日本三代実録』の総称)終了時点で、正一位、従一位、正二位、従二位、正三位、従三位、正四位(上・下)、従四位(上・下)、正五位(上・下)、従五位(上・下)、正六位(上)の15階級で、最高位の正一位には16柱が列せられています。
本来は、天皇が神様に位を付けるというもので、正一位のさらに上には位階なし、ということから位階を超えた別格の神として、伊勢大神(伊勢国 神宮)、日前神(紀伊国 日前神宮)、国懸神(紀伊国 國懸神宮)と定められています。
天皇の即位などで、神威の授与、さらには神階の一斉格上げが行なわれたため、数多くの神様が、正一位までランクアップ。
国家に対する功績が特に顕著な場合は正一位という曖昧な基準だったため、ときの権力者によって、どんどんレベルアップが行なわれたというわけです。
たとえば稲荷と名の付く神社に行くと、正一位稲荷神という赤い幟を目にすることがありますが、現在は正一位の稲荷神も天長4年(827年)に淳和天皇から従五位下を授けられたのが位を徐々にあげ、天慶5年(942年)の諸神に対する授位で正一位に叙せられので、最上位まで特進したことがわかります。
全国の稲荷社が正一位をアピールできるのは、建久5年12月2日(1195年1月14日)、後鳥羽天皇が伏見稲荷に行幸の際、稲荷神が尊信すべき五穀衣食の守護神ということで、「本社勧請の神体には『正一位』の神階を書加えて授くべき」旨が勅許されたからなのです(実際に稲荷神ブームで諸国に勧請されたのは江戸時代です)。
富士山、伊豆諸島の火山活動が活発化した9世紀には、富士山の主神である駿河国・浅間大神の格上げがたびたび行なわれ、朝廷が噴火の沈静化を願っていたことがよくわかります。
岩手県奥州市の駒形神社に祀られる駒形神は、9世紀に正五位下から従四位下にランクアップしていますが、東北では最上位の神階で、蝦夷(えみし)征討の最前線の守護神として坂上田村麻呂にも尊崇を受けたということも大きく影響しています。
近世には、武家政権の力が強くなったことから、豊臣秀吉(豊国大明神)、徳川家康(東照大権現)は人物神として正一位を朝廷から与えられていますから、時代と世相を反映した位であることもよくわかります。
明治時代、神社、神道を国家統制に組み込むなかで、神格ではなく、神社に与えられる社格の方が重視され、神階の制度は廃止されています。

六国史における正一位の神様
- 神産日神、高御産日神、玉積産日神、足産日神(宮中・八神殿=現在は皇居の神殿)
- 松尾神(山城国・松尾大社)
- 今木神(山城国・平野神社)
- 賀茂別雷神(山城国・賀茂別雷神社)
- 賀茂御祖神(山城国・賀茂御祖神社)
- 春日神(大和国・春日大社)
- 大己貴神(大和国・大名持神社)
- 大神大物主神(大和国・大神神社)
- 石上神(大和国・石上神宮)
- 枚岡天児屋根命(河内国・枚岡神社)
- 伊波比主命神(下総国・香取神宮)
- 建御賀豆智命神(常陸国・鹿島神宮)
- 大比叡神(近江国・日吉大社)
| 神様にも階級がある! 神階1位の「正一位」の神様は!? | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |