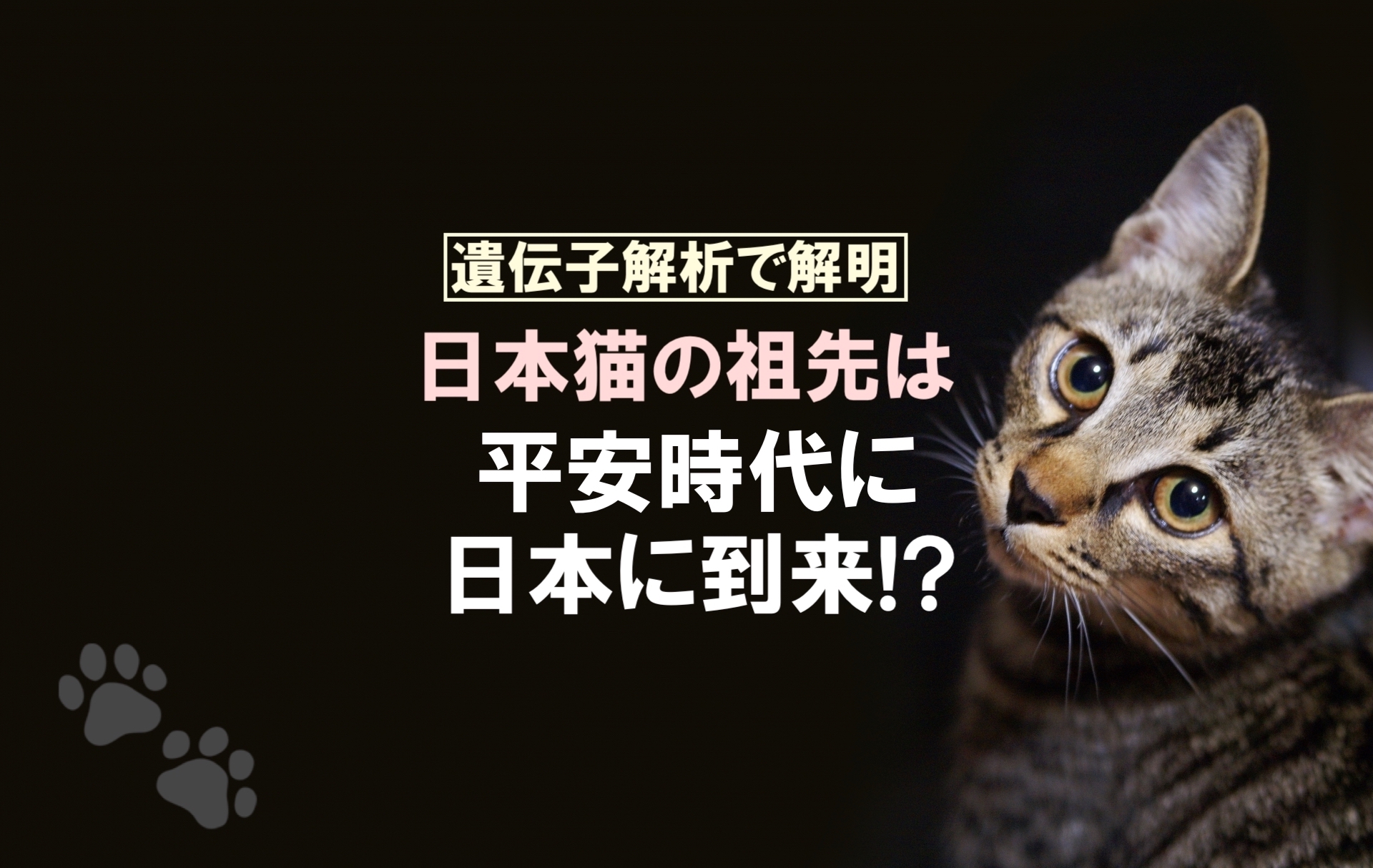日本猫(和猫)には血統書がなく、すべて雑種です。古代、日本列島にはヤマネコは生息していたものの(食用にもなっていました)、イエネコはいませんでした。アニコム先進医療研究所研究開発部が猫の血液から遺伝情報を解析したところ、900年前の平安時代に九州に本格的に渡来したことがわかっています。
遺伝子解析で探るネコたちのルーツ

壱岐島(長崎県)で弥生時代のカラカミ遺跡からイエネコと見られる骨が出土し、イエネコの伝来が弥生時代に遡るのかと話題になりましたが、もしイエネコの骨としても朝鮮半島から渡来したレアなケースで、繁殖、普及することはなかったということに。
壱岐島は3世紀の『魏志倭人伝』で、魏の使者が邪馬台国を目指して朝鮮半島から九州に渡る際、対馬国から一支国(いきこく)に渡ったと記されるように、古代、海のシルクロードにおける交流・交易の拠点だったことから、イエネコもいち早く伝来したのだと推測されます。
アニコム先進医療研究所研究開発部の松本悠貴(まつもとゆき)研究員などの研究(遺伝子・ゲノムの観点から、ネコをはじめとした哺乳類の形質の多様性の分子基盤や集団の歴史について研究)では、全国各地の日本猫71匹から血液などを採取、遺伝情報を抽出して解析、日本猫がいつ、どこから伝搬したのかを科学的に調査しました。
これまで、考古学的には壱岐島のカラカミ遺跡でのイエネコと見られる骨(弥生時代1世紀〜3世紀のほかには、国内の遺跡では7世紀ころの骨しか見つかっていません。
『古事記』、『日本書紀』にはイエネコの記述はなく、文献資料での初登場は『日本霊異記』に、慶雲2年(705年)、豊前国(現・福岡県東部)の膳臣広国(かしわでのおみひろくに)が、死後、イエネコに転生し、息子に飼われたとあるのが最初です。
飼育された猫の記録としては昌泰2年(889年)、宇多天皇による黒猫の飼育日記がありますが、「唐土渡来の黒猫」という注記があり、当時のイエネコはまだ「唐猫」と呼ばれる舶来品だったこともわかっています。
松本悠貴研究員の科学的な研究では、日本猫の有する遺伝子が、何世代前から受け継がれている遺伝子なのか、その世代の遺伝子にどの程度の多様性があるのかを解析することによって、生息していた時代、集団の数なども明らかになるのだとか。
研究の結果から、平安時代末期に九州に本格的に渡来し、やがて本州に広まり、江戸時代になると爆発的に増えていることが判明。
文献などの研究では、豊臣秀吉が日本猫を飼っていましたが、まだまだ普及までには至らず、天下泰平の江戸時代に普及し、養蚕農家などではネズミ対策で飼育していたこともわかっています(ネズミの被害が拡大した際にはイエネコの売値が高騰)。
こうした歴史学的な考察の裏付けともなったのが、松本悠貴研究員の遺伝子解析です。
ちなみにイエネコは1万3000年前にリビアヤマネコが家畜化したもので、シルクロードを経て中国に伝来、唐代(8世紀頃)に中国で普及したイエネコの飼育が、日本に伝搬したのだと推測できます。
中国から伝わったものとして仏教、漢字、茶などは有名ですが、日本猫のルーツも、海をわたってやってきたイエネコということに!

| 日本猫の「祖先」は、平安時代に日本に到来!? | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |