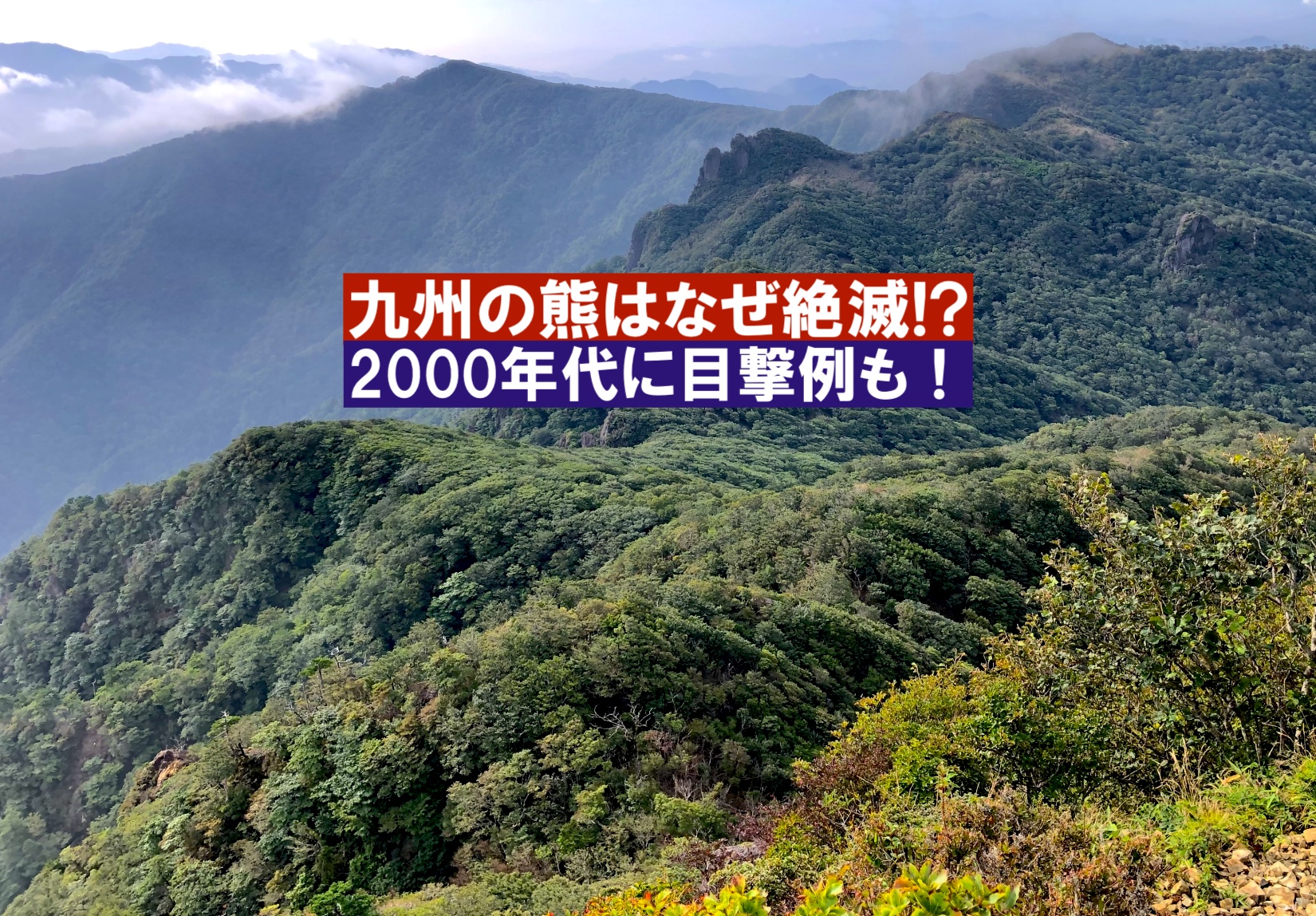かつて九州にもツキノワグマが生息していました。宮崎県高千穂町では昭和16年に狩猟で熊を獲ったという記録もあり、地元では昭和30年頃まで熊を見かけたという話もあるので、絶滅したのもそんなに昔のことではありません。ではなぜ、九州に生息していたツキノワグマは絶滅したのでしょう。
最大の理由は人工林が多く、実の成る木が少ないから

2000年〜2010年には、高千穂町の祖母・傾(そぼかたむき)山系で、ツキノワグマを目撃したという情報が数多くありますが、証拠がないため、あくまで「らしき動物が生息」ということになっています。
専門家の分析でも「熊である可能性が極めて高い例」が3例、十分高い1例、高い2例で、目撃例のうち6例で熊である可能性が大となっています。
実は1930年代までは、九州には熊はいないというのが学説でしたが、山仕事の人や、登山家が反論し、熊猟が行なわれていることを紹介して、ようやくツキノワグマの生息が認知されたという歴史もあります。
ただし、かつてツキノワグマが生息していた熊本県、大分県、宮崎県では「絶滅」としています。
環境省も2012年に絶滅を宣言しています。
目撃例は、アナグマなどとの見間違えと考えているようです(ただし、目撃者の中には山仕事の人も)。
東北を含め全国でツキノワグマの増加、里山に降りてくる事態が報告される中、九州からは、「再発見」のニュースは聞こえてきません。
なぜ九州のツキノワグマは絶滅したのでしょう。
理由のひとつは人工林の多さです。
冬眠前の熊は、ブナ、コナラ、ミズナラなどの実を食べるので、杉や檜などの人工林の山では命を長らえることができません。
綾町など照葉樹林で名高い宮崎県でも、人工林が57%。
熊本県61%、大分県51%で、全国平均の40%をかなり上回っています。
九州の山は人工林が多く、野生動物には少し住みづらい環境ということに。
地形図を見るとわかるのですが、九州の山は分断されていて、移動しづらいという側面も。
九州島内に本州の熊が泳いで渡る可能性も、関門海峡の潮の流れを考えると考えづらく(ヒグマは北海道の稚内西海岸から利尻島へ泳いで渡った記録があるので、可能性はゼロではありませんが)、絶滅、あるいは限りなく絶滅に近い状態であることがわかります。

| 九州の熊はなぜ絶滅!? 2000年代に目撃例も! | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |