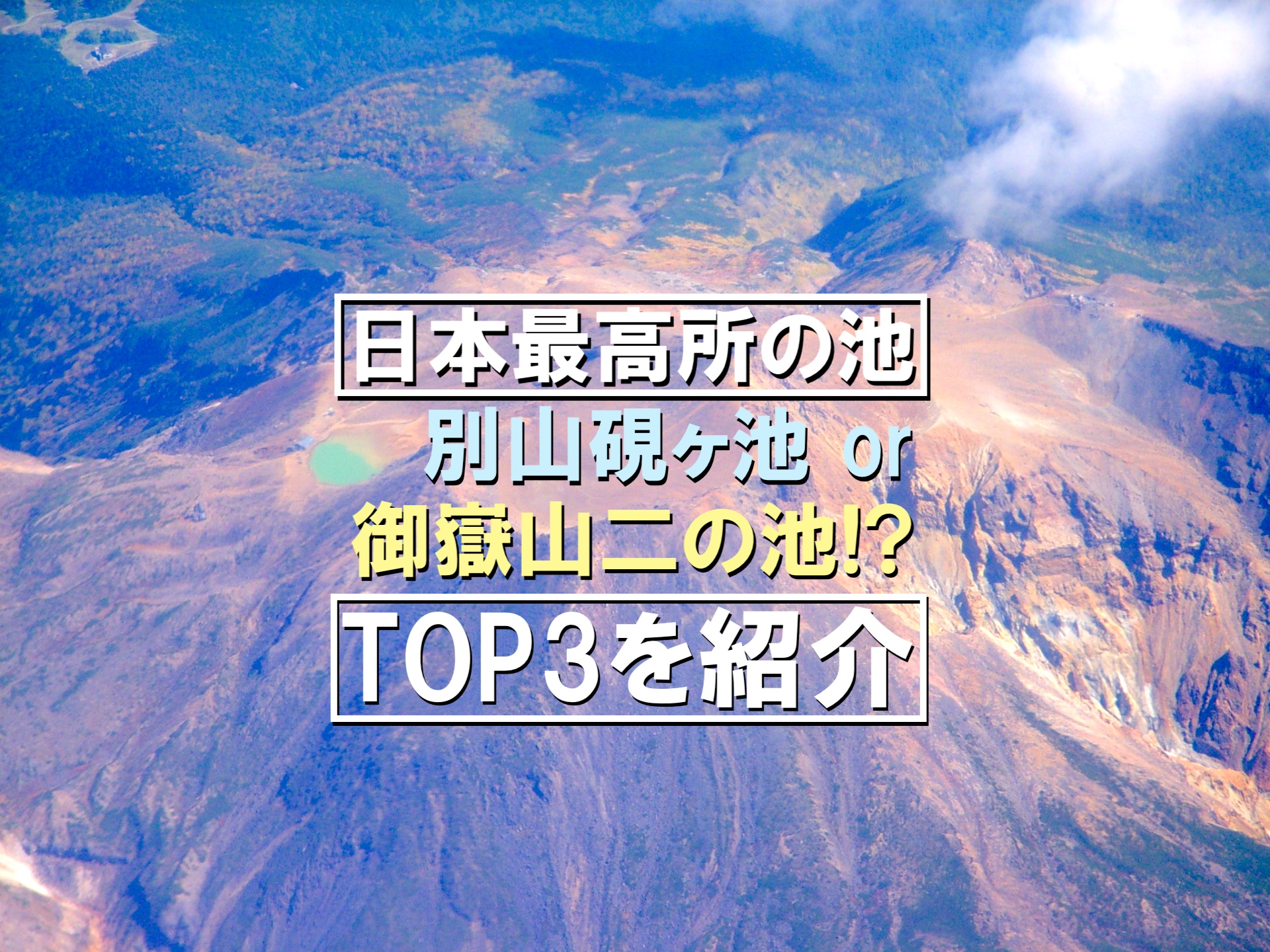日本最高所の池はどこにあるのでしょう? 富士山頂に通年見られる池があれば、文句なしに日本一。初夏に表富士側(静岡県側)から富士登山をされた人なら、富士宮口山頂近くに、「このしろ池」があったことにお気づきでしょう。これが、日本最高所の池といえば、実はそうではないのです。
日本最高所の池は富士山頂に?

「このしろ池」について江戸時代に編纂された『駿河国新風土記』では、
「時ニヨリテ水ノアルコトモアリ。又ナキコトモアリテ、魚ナドノ住ムベキ処ニアラズ」と記されています。
わざわざ魚が棲まないと注記したのは、コノシロという魚が棲むという伝承があったからにほかなりません。
富士山の8合目以上は今も富士山本宮浅間大社の神域(境内地)ですが、その祭神・木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと=浅間大神)の眷属(けんぞく=従者)とされるのが、コノシロです。
本来は海の魚なので富士山頂に生息する可能性はありません。
この「このしろ池」、富士山の登山ガイドに聞いても、
「雪解け水があるうちは池だけど、真夏には乾いてしまってブルドーザーの荷揚げ道にもなってしまいます」
とのこと。
これが、『駿河国新風土記』にいう「ナキコトモアリテ」なのです。
下の地図で郵便局マーク(夏山シーズンだけ開局する日本最高所の郵便局、富士山頂郵便局/静岡県駿東郡小山町須走富士山頂)の左側に「このしろ池」があるわけですが、地図には記載されていません。
富士登山ガイドも「幻の池」と喧伝(けんでん)しています。
では、立山連峰・別山の硯ヶ池なのか?

続いて、市販のガイドブックに「日本最高所にある池」として立山連峰・別山山頂(富山県)の硯ヶ池(すずりがいけ)だと記されているものがあります。
別山は、北側の峰が2880m、南側の峰が2874m。
2つの峰を結ぶほぼ平坦な尾根上に硯ヶ池があります。
たしかにこの池は、「このしろ池」とは異なり、しっかりと国土地理院の地形図にも表示されています。
標高は2850mほど。
これが最高所と思いきや、実は木曽御岳山(御嶽山・3063.61m)の山上にこれを上回る高山湖がああったのです。
あったと過去形にしているのは、2024年10月に消滅してしまったから。
復活できなければ、硯ヶ池が日本最高所の池ということになります。
真の日本一は、御嶽山二ノ池!

複合成層火山である御嶽山は、痛ましい爆発による事故が脳裏をよぎりますが、山頂には一ノ池から五ノ池まで5つの火口湖があります。
最高所にある一ノ池は標高2990mですが、やはり涸れていることが多く、日本最高所とは認定されません。
国土地理院の地形図を見ても、一ノ池は地図上も涸れてしまっていますが、二ノ池はしっかりと地図に記載。湖畔には2908mの標高点があります。
池自体の標高は、2905mで、この二ノ池が日本最高所の池。
池の横には「二ノ池山荘」があり、 山頂に一番近い山小屋となっています。
御嶽山の爆発で、現在、二ノ池は、火山灰に埋もれましたが、徐々に、往時の姿を取り戻しつつありましたが、2024年秋に消滅。
火山灰が水と一緒に流れ出して、池の部分(凹地)を埋め尽くしたため、過去に水があったと推測される一ノ池同様に、消滅してしまったという状態になっています(日本最高所の池、御嶽山・二ノ池に異変あり! 昨秋に消滅!? を参照)。
3位は乗鞍岳山頂の権現池

似たような火山地形の乗鞍岳を念のためにチェックすると、乗鞍岳山頂近くにある最高所の火口湖・権現池(トップの画像は乗鞍山頂から眺めた権現池と白山)で、標高は2845mほど。
硯ヶ池にあと一歩で、国内第3位の高山湖と認定できます。
乗鞍岳には、俗に「乗鞍23峰」というように山頂部に23峰があるといわれていますが、7つの池(火口湖)もあり、そのうちもっとも高所にあるのが権現池です。
御嶽山の二ノ池に次ぐ日本第2位の標高という記述も見かけますが、硯ヶ池に次ぐ、3位というのが正解です。
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |