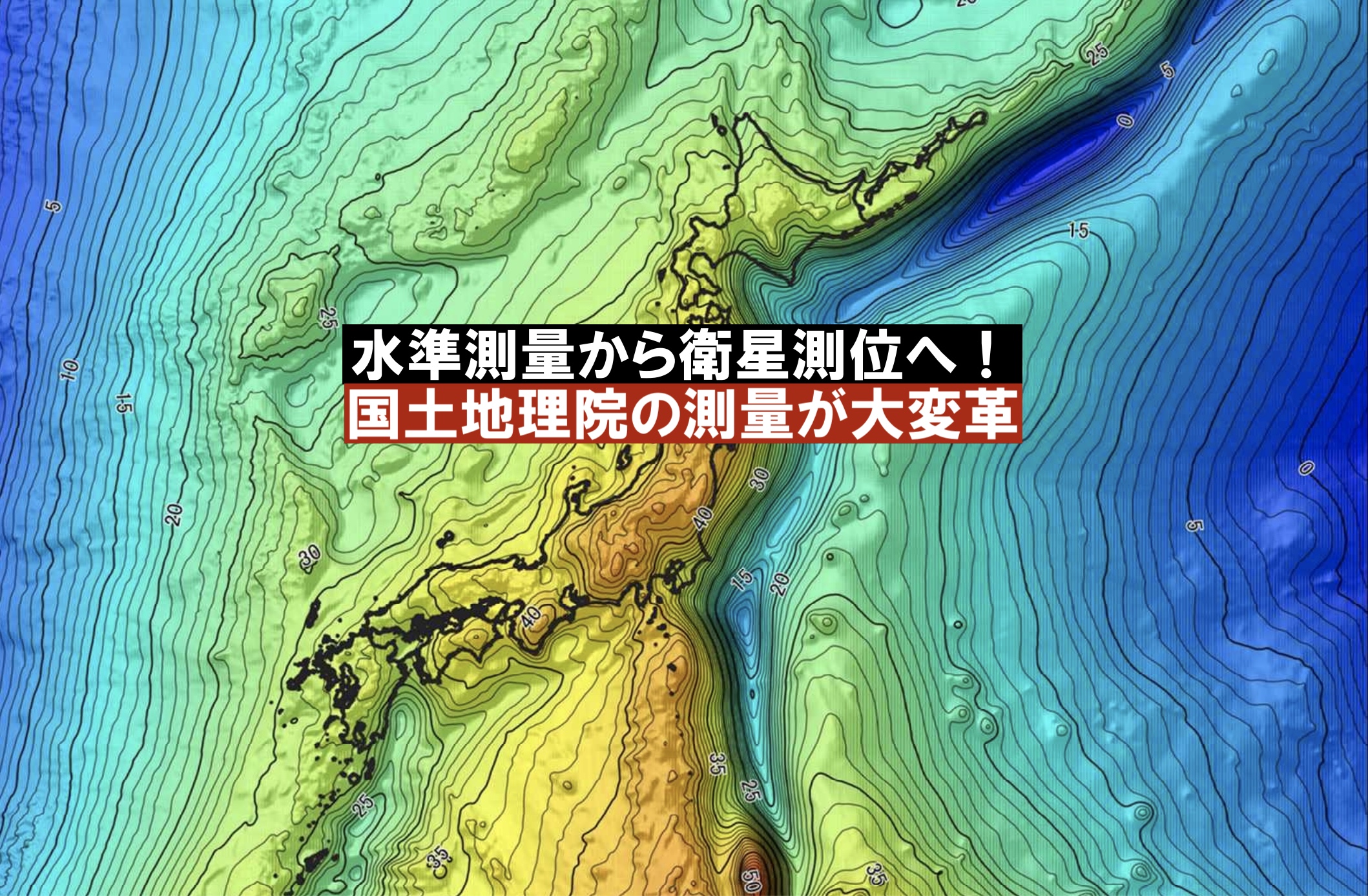国土地理院は、令和7年4月1日「国土地理院で管理する電子基準点、三角点、水準点等の基準点の標高について、衛星測位を基盤とする最新の値に改定します」。あまり知られていませんが、実は、明治16年に水準測量が始まって以来の地図測量の大変革ということになります。
水準測量が終了し、衛星測位がスタート!

富士山の山頂などを含め、日本国内の標高は、東京湾の平均海面を0mとし、日本水準原点(東京都千代田区永田町1丁目にある日本水準原点標庫内に設置)を基点に、全国の主要な国道などに一定の間隔で設置された1万6000点ほどの水準点を、水準測量によって求めています。
実は、この日本水準原点の数値は、一定でなく変遷しています。
明治24年に24.500mだったものが、関東大震災後に少し沈下して昭和3年には24.414mに、さらに東日本大震災でも沈下して平成23年には24.3900mという標高になっています。
現代の測量技術を使っても、マンパワーの問題もあり、水準測量で全国を測量するには10年の歳月が必要です。
その上、地震大国・日本では、地殻の変動も大きくその影響が標高に累積することになります。
しかも水準測量では原点の東京から離れれば離れるほど誤差が大きくなるという欠点がありました。
こうした課題を解消したのが衛星測位を基盤とする標高体系で、まず、国土の精密なジオイド・モデルを作成。
ジオイド(Geoid)とは、平均海面を仮想的に陸地へ延長した面のこと。
つまり、このジオイド・モデルがあれば、全国どこの地点でも、その標高は、衛星測位で決まる高さ(楕円体高)からジオイド高を引くことで、簡単に求めることができるのです。
精密で詳細なジオイド・モデルを作成するため、国土地理院は令和元年〜令和5年まで民間機をチャーターして総飛行距離13.9万km、飛行時間1316時間にも及ぶ航空重力測量を実施しています。
こうして高精度なジオイド・モデルが誕生したことで、令和7年からいよいよ「新しい標高体系」へと移管したのです。
| 水準測量から衛星測位へ! 令和7年、国土地理院の測量が大変革 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |