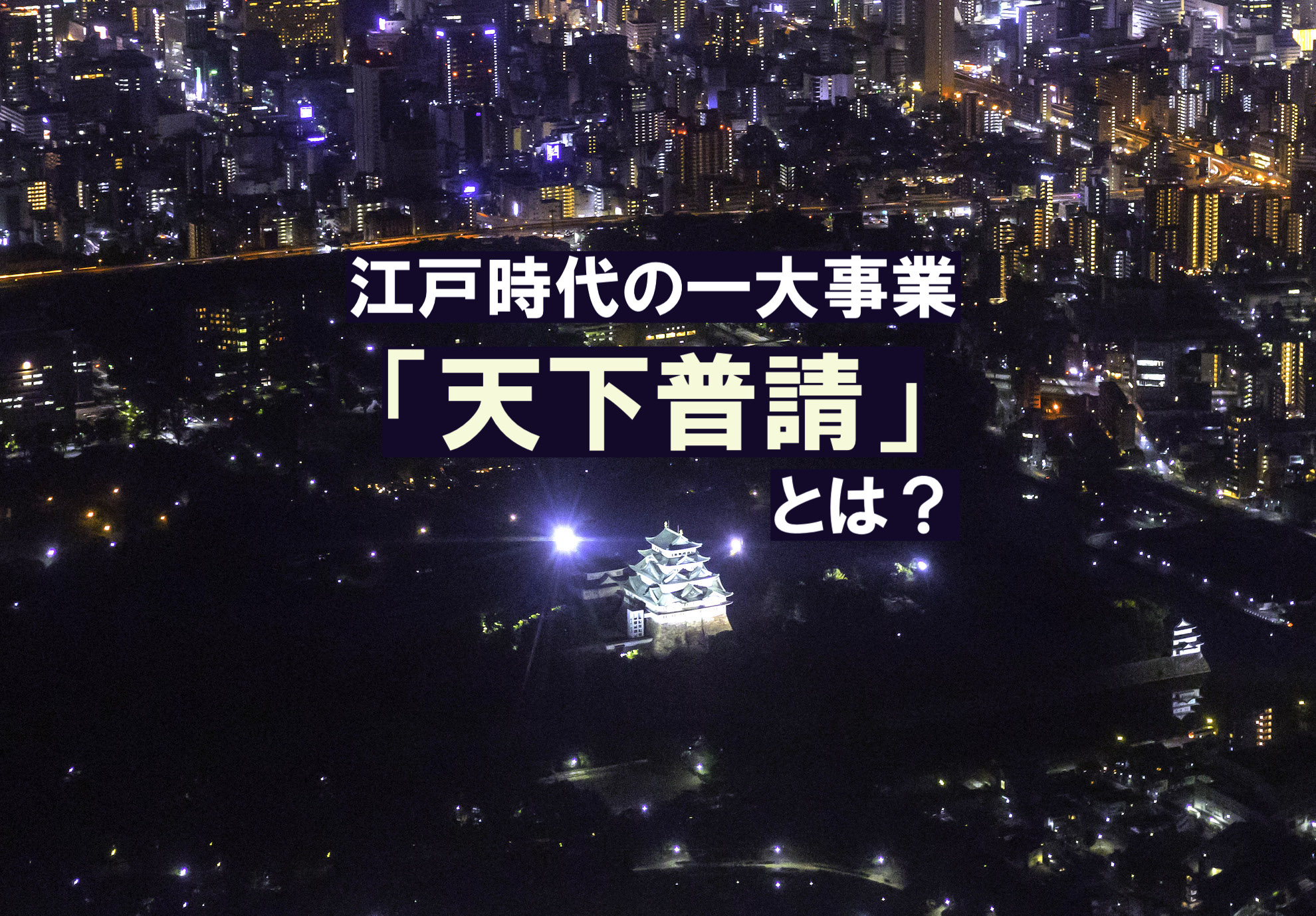江戸に幕府を開いた徳川家康は、利根川東遷事業、江戸の上水道整備など数多くの土木プロジェクトも行なっていますが、西日本などの主要な拠点におもに外様の諸大名に命じて、新たな城を構築しました。この大事業が天下普請(てんかぶしん)で、江戸城、名古屋城、大坂城など全国13城が築かれています。
おもに西国の諸大名を動員して徳川幕府が築城を命じた城

普請(ふしん)とは建築のことで、天下普請とは、まさに徳川幕府の国家プロジェクトを示す言葉です。
近世の城郭は、その威厳を示すための天守を石垣(天守台)の上に構築、また城門の周辺にも防備のために枡形などを築いたため、多くの石材が必要になりました。
伊豆や小豆島で切り出した石を、舟で運ぶという大事業となったため、とくに動員された外様大名たちに対する経済的負担は増大しました。
諸大名には最新の築城技術を目にできるというメリットはありましたが、財政の赤字を余儀なくさせ、さらには徳川幕府への忠誠度を競う場ともなったため、精神的、政治的な消耗度もあったと思われます。
天下普請で築城された城の大手門などメインとなる登城路の枡形虎口には、登城する人を驚かせるような「鏡石」(かがみいし)と通称される巨石が置かれましたが、これも築城を命じた徳川幕府の指示ではなく、諸大名が担当した石垣の部分に、採算を度外視して巨石を運んだもの。
巨大な石を配し、ひときわ目立つことで、徳川家への忠誠心をアピールしたのです。
天下普請で築かれた大坂城(現在の大阪城公園)で最大の蛸石(桜門枡形虎口)は、表面積36畳という巨大な石ですが、岡山藩主・池田忠雄(池田輝政の三男、母は徳川家康の次女・督姫)が運び込んだもの。
2位の肥後石、3位の振袖石も池田忠雄の担当なのでその忠誠心がよくわかります。
母が家康の娘であっても、外様大名という立場、しかし西への備えとしての準親藩の扱いという微妙な立場ゆえに、この巨石3個配置につながったのでしょう。
岡山藩主・池田忠雄のメリットは、ここで学んだ石垣の技術を岡山城の改修に活かされたことでしょう。
石垣に使われた石に刻印があるのは、大名が運んだ石を間違えないためですが、当然、盗難防止の役割をも果たしていました。
大坂城の近世的な城郭の改築は、大阪の陣後で豊臣家は滅亡していますが、名古屋城の築城は(有名な清洲からの城下町の大移動「清洲越し」)、大坂城に豊臣秀頼が陣取る最中だったため、名古屋城と伊勢湾とをつなぐ堀川運河の開削を担当した福島正則(豊臣秀吉の死後、いち早く家康方に与した大名)は、同じ秀吉子飼いで尾張国出身の加藤清正(名古屋城では石垣担当)に「家康の暮らす江戸城は仕方がないが、家康の庶子(九男・徳川義直)のための名古屋城まで手伝わされるのはかなわん」とぼやいた逸話が残されていますが、動員された諸大名のホンネはそうした感じだったのだと推測できます。
ちなみに堀川の掘削では石高1000石当たり労働者1人の供出が義務付けられたため、福島正則の広島藩は49万8000石だったので、単純計算しても人足だけでも500名近くを確保する必要があり、愚痴が出るのもうなづけます。

| 江戸時代の一大事業「天下普請」とは? | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |