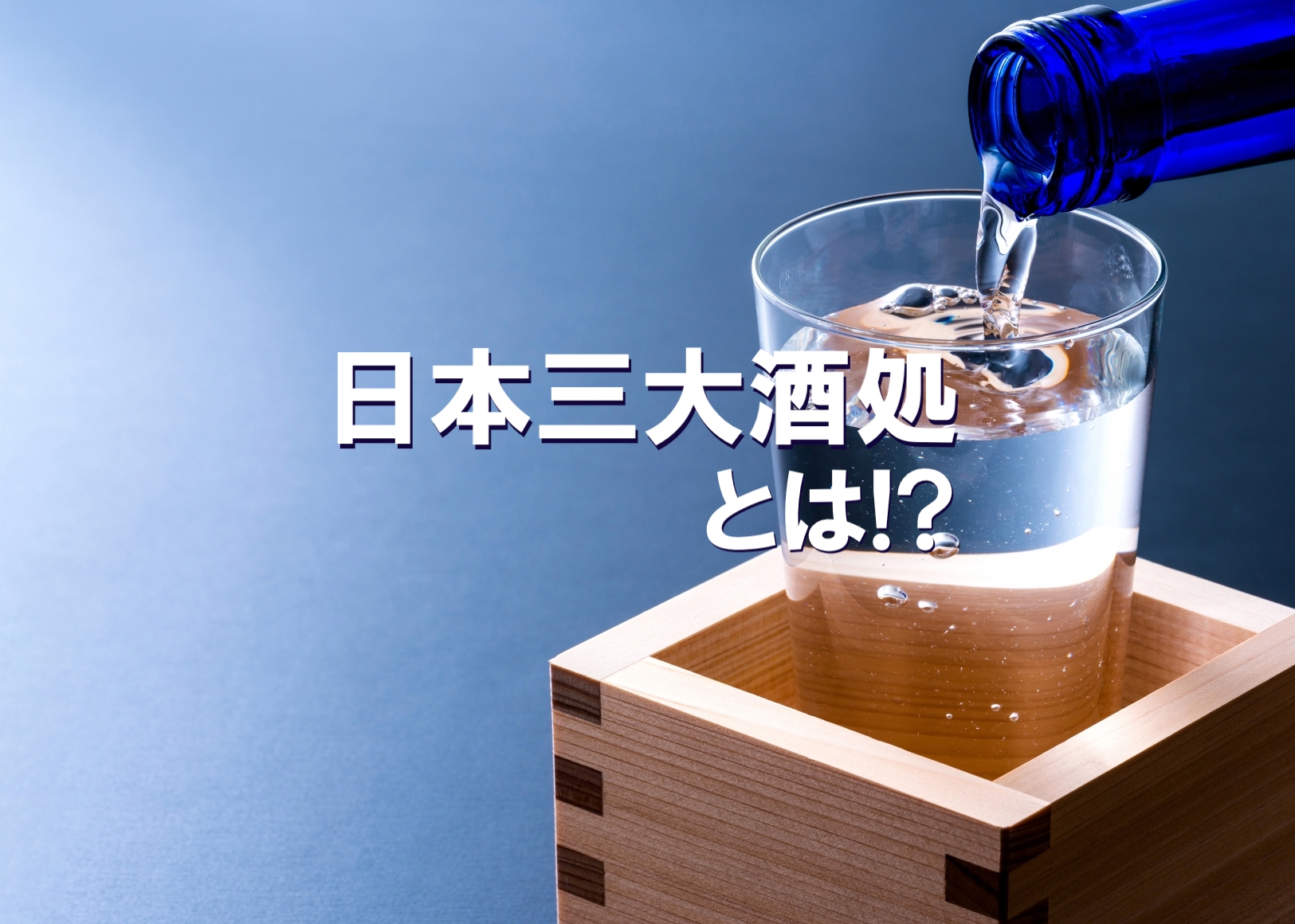日本酒の醸造には酒造好適米(酒米)と、良質な水が必要ですが、必要な水の総量は米の総重量のなんと50倍にもなり、しかもその硬度の違いで辛口、柔らかな味わいといった個性を生み出します。日本三大酒処と通称されるのは伏見(京都府京都市伏見区)、灘(兵庫県神戸市灘区)、そして西条(広島県東広島市)です。
伏見|京都府
仕込み水の硬度:80前後(中硬水)
仕込み水の特徴:環境省の名水百選「伏見の御香水」(ふしみのごこうすい)に代表される伏流水が多い土地柄(伏見という地名もかつては伏流水を表す「伏水」でした)
「桃山丘陵をくぐった清冽な水が、水脈となって地下に深く息づき、山麓近くで湧き水となる」(伏見酒造組合)
砂礫層が湧出するカリウム、カルシウムなどをバランスよく含んだ水
酒造好適米:京都産酒造好適米「祝」(いわい)は吟醸酒向けの品種
醸す酒の特徴:きめ細かく、まろやかな風味で「女酒」 とも称されています
主な酒造メーカー:黄桜、キンシ正宗、月桂冠、宝酒造、山本本家
灘|兵庫県
仕込み水の硬度:100前後(中硬水)
仕込み水の特徴:古来「宮水」(「西宮の水」の略称)と称される名水で、江戸時代末期の天保11年(1840年)、酒造家の山邑太左衛門(やまむらたざえもん)が発見
六甲山の花崗岩層を通って湧き出る伏流水で、軟水の多い日本では硬度が高いのが特徴
リンやカリウム、カルシウムなどのミネラルが豊富に含まれているほか、鉄分が少ないのが特徴
酒造好適米:兵庫県産「山田錦」は、タンパク質の含有が少ないため、雑味が少なくなる特長が
醸す酒の特徴:硬水が醸すキレのあるスッキリとした銘酒で、「男酒」とも称されています
新酒の間は少し角が立ちますが、貯蔵・熟成を経て秋には香味が整いまろやかな味わいに(「秋あがり」と呼んでいます)
主な酒造メーカー:大関、日本盛、白鷹、菊正宗酒造、松竹梅酒造、白鶴酒造、沢の鶴、大澤本家酒造
江戸時代、江戸で飲まれる酒の8割は灘の酒でした
西条|広島県
仕込み水の硬度:70前後(中硬水)
仕込み水の特徴:龍王山の伏流水で、流紋岩と花崗岩の入り混じった地層を通過し、酒造りに向かないとされる軟水が、酒蔵通り一帯では適度な硬度に変化
酒造好適米:広島県産「山田錦」など
醸す酒の特徴:軟水に近い柔らかな中硬水のため、甘すぎず辛すぎず、それでいて旨味のある調和のとれた日本酒に
主な酒造メーカー:賀茂鶴酒造、白牡丹酒造、賀茂泉酒造、福美人酒造、賀茂輝酒造、山陽鶴酒造、西條鶴醸造
| 日本三大酒処とは!? | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |